長時間労働や体力的な負担から、飲食業界以外に転職したいと考える方は多くいます。飲食業界はさまざまな課題を抱えていますが、テクノロジーの導入やビジネスモデルの変革により、新たな可能性も広がっています。飲食業を続けるべきか悩んでいる人は、今後の飲食業界の進化を理解したうえで判断すべきです。
この記事では、飲食業界の現状分析から今後の市場動向、直面する課題、新たなビジネスモデルまで包括的に解説します。記事を読めば、飲食業界の将来性を把握でき、転職するべきか続けるべきか判断が可能です。飲食業界以外への転職を決断する前に、業界の変化と自分のキャリアパスを照らし合わせてみましょう。
飲食業界の現状と今後の市場動向

飲食業界の現状と今後の市場動向について、以下の視点で解説します。
- コロナ禍を経た飲食業界の変化
- 飲食業界の市場規模と成長率
- 外食と中食の市場シェア比較
コロナ禍を経た飲食業界の変化
コロナ禍の感染対策や生活様式の変化を受け、業界全体で新たなビジネスモデルやサービスが広がっています。顕著だった点は、外食の代替となるサービスや衛生意識の高まりに応じた取り組みの増加です。コロナ禍を経た飲食業界の変化は、以下のとおりです。
- テイクアウトやデリバリー需要の増加
- キャッシュレス決済の普及と加速
- 衛生管理の厳重化
近年はデリバリー専門のゴーストキッチンや、1つのキッチンで複数のブランドを展開するバーチャルレストランが台頭しています。スタッフの業務負担の軽減と人件費削減を図ることを目的に、セルフサービス形式の店舗運営も増加しました。
飲食業界の市場規模と成長率

飲食業界の市場規模は2022年時点で26兆円となっており、コロナ禍前の80%まで回復しています。2023年には飲食業界の市場規模が29兆円に拡大し、2025年には33兆円程度まで成長すると予測されています。業態別では、ファストフード市場が最も早く回復し、前年比108%の成長を達成しました。
居酒屋業態は回復が遅く、2019年と比較して市場規模は65%程度にとどまっています。テイクアウトやデリバリーを含む中食市場は、年平均5%以上の成長率が続いています。中食市場の中でも、フードデリバリー市場は2020〜2023年の数年で2.5倍に急成長しました。
2020年以降、飲食店の倒産件数は累計1万店舗に達し、廃業を含めると5万店舗が市場から撤退しています。飲食業界の新規出店も減少傾向にありましたが、2023年後半から回復の兆しを見せ始め、前年比115%の出店数となりました。
インバウンド需要の回復も飲食業界の市場に大きな影響を与えています。2023年後半からは、都市部の飲食店の売上が前年比130%以上を記録しました。外国人観光客の増加が、都市部の飲食店にとって大きな追い風となり、売上回復を加速させています。
» 飲食業界の今と未来を徹底解説!
外食と中食の市場シェア比較
外食産業の市場規模は、2019年で26兆円でしたが、コロナ禍の影響を受けた2020年には20兆円まで縮小しました。2022年には23兆円まで回復したものの、コロナ前の水準には戻っていません。一方で、中食市場はコロナ禍でも成長を続け、2022年には11兆円に拡大しています。
市場シェアの比率も変化しており、外食と中食の割合がコロナ前の70対30から65対35に変わり、中食の比重が増しています。中食市場では高付加価値商品の需要が拡大しており、プレミアム弁当や惣菜の分野が好調です。
外食産業でも、店内飲食の回復を図ると同時に、デリバリーやテイクアウトなどの中食領域へのビジネス拡大が欠かせません。多くの飲食チェーンが、実店舗にECやテイクアウト、デリバリーを組み合わせたハイブリッド型の営業モデルを導入しています。
飲食業界が直面している課題

飲食業界が直面している課題は、以下のとおりです。
- 原材料費や経費の高騰
- 人手不足と労働環境の改善
- 顧客ニーズの多様化
原材料費や経費の高騰
食材価格の高騰は、飲食業界にとって深刻な問題となっています。小麦や油脂類、輸入食材の価格上昇は、パスタやパンなどを提供する店舗の原価率を押し上げ、利益率を圧迫しています。
電気代やガス代の高騰により、調理や店舗運営にかかる光熱費のコストも増加しました。調理に多くのエネルギーを使用する居酒屋や焼肉店では、光熱費高騰の影響が顕著に表れています。人件費の増加も、飲食業界にとって深刻な問題です。
最低賃金の引き上げにより、アルバイトやパートタイマーの人件費が上昇しており、経営負担の要因となっています。飲食業は人手に依存する割合が高く、自動化が進みにくいため、人件費の上昇は避けられない課題です。しかし、競争の激しい市場では価格転嫁が難しく、値上げによる客離れを防ぐ工夫が求められます。
人手不足と労働環境の改善

飲食業界における人手不足は、長時間労働や低賃金、不規則なシフトなどの労働環境の問題が主な原因です。特に20代の若手にとっては、長期的なキャリアを築きにくい業界と見なされやすく、人材の確保と定着が困難になっています。
最低賃金の上昇により経営側の人件費負担も増加しているため、賃上げによる人材確保は難しい状況です。人手不足と労働環境の課題に対して、飲食業界では改善に向けて以下の取り組みが進められています。
- 福利厚生の充実による従業員満足度の向上
- 教育研修制度によるスキル向上と定着支援
- キャリアパスの明確化による将来像の提示
- 設備投資による作業環境の快適化
- 柔軟な勤務体系による働きやすさの向上
多くの飲食店で外国人労働者への依存度が高まっていますが、言語や文化の壁が新たな課題となっています。多言語対応のマニュアル作成や異文化理解のための研修も必要です。
働き方改革の影響を受けて、シフト管理や業務オペレーションのデジタル化も進められています。シフト管理アプリやPOSシステムの高度化によって、少人数でも効率的な店舗運営が可能になってきました。
最近では従業員のメンタルヘルスケアの重要性も認識されつつあります。心理的サポート体制の整備は、離職率の低下や職場への定着率向上につながる取り組みとして注目されています。
» 飲食業から転職するための方法を紹介
顧客ニーズの多様化
ベジタリアンやグルテンフリーなど、特定の食事スタイルを求める消費者が増加しています。おいしさや安さだけで選ばれていた時代から、より個人の価値観に合った飲食店が選ばれる時代へと変化しているためです。
最近の飲食業界では、SNSで映える個性的な料理や、一人で食事を楽しめる「ソロダイニング」への対応も注目されています。地域の特色や文化を反映したローカルフードの人気も高まっており、画一的なメニューだけでは競争力の維持が困難な状況です。
飲食業界では「高級志向」と「低価格志向」の二極化が進んでおり、中間価格帯の店舗では差別化が一層求められています。時間帯や曜日によって変化する客層への対応も必要であり、柔軟な営業戦略が不可欠です。
飲食業界の今後のビジネスモデル

飲食業界では、社会環境や消費者ニーズの変化への対応を目的とした、新たなビジネスモデルの導入が進められています。飲食業界で注目される今後のビジネスモデルは、以下のとおりです。
- テクノロジー導入による効率化
- フードデリバリーとテイクアウトの拡大
- サブスクリプション型のビジネスモデル
- 外国人観光客の回復によるインバウンド需要
- 地方や郊外での新たなビジネス
テクノロジー導入による効率化
飲食業界では、人手不足やコスト高騰などの課題解決に向け、テクノロジーを利用した業務効率化を進めています。注目されているシステムや機器は、以下のとおりです。
- セルフオーダーシステムやキオスク端末
-
来店客が自ら注文を完結できる端末の設置により、注文ミスの削減やピーク時の混雑緩和が可能です。人的リソースの節約にもつながります。
- AIによる需要予測システム
-
過去の売上データや天候、イベント情報などをAIが解析し、来店数や必要な食材量を自動で予測します。フードロスや仕入れの無駄の削減が可能です。
- クラウド型POSレジ
-
リアルタイムで売上や客層データを集計・可視化でき、複数店舗の統合管理にも対応しています。曜日別の来店傾向や客単価を分析し、効果的な販促やメニュー改善に有効です。
- スマートフォンによる遠隔管理システム
-
オーナーや本部が離れた場所からでも、売上状況や在庫、シフト状況などを確認できる仕組みです。店舗に常駐せずに経営を行えるため、多店舗展開との相性も良好です。
- ロボット調理機器・自動フライヤー
-
定量の食材を自動で計量したり、決まった温度で調理したりできるため、調理品質のばらつきがなくなります。一定のクオリティを維持できるため、新人スタッフの即戦力化が可能です。
- キャッシュレス決済
-
クレジットカードやQRコード決済によって、現金管理やレジ締め作業の手間を軽減できます。スムーズな会計で客席の回転率の向上にも貢献します。
- IoT機器
-
温度や湿度、照明をセンサーで自動制御し、エネルギーを抑えつつ快適な店内環境の維持が可能です。閉店後の電源管理なども自動化されるため、人的ミスの防止にもつながります。
テクノロジーの活用は、業務負担の軽減や人件費の削減だけでなく、サービスの質向上や顧客満足度の向上にも直結します。
フードデリバリーとテイクアウトの拡大

コロナ禍の後、フードデリバリーの市場規模は2022年時点で8,000億円まで成長しました。フードデリバリー市場では、Uber Eatsや出前館、Woltなど多数のサービスが成長を牽引しています。デリバリーサービスには25〜35%の手数料がかかるため、経営を圧迫するリスクには注意が必要です。
デリバリーにかかるコスト削減のため、自社アプリやWebサイトを活用し、直接注文の仕組みを構築する飲食店も増えています。飲食業界では、デリバリー・テイクアウト専門ブランドの構築や共同配送など、収益性を高める仕組みも導入され始めています。
サブスクリプション型のビジネスモデル
サブスクリプション型のビジネスモデルは、月額固定料金を支払うことで、決まった回数の食事やドリンクを楽しめる仕組みです。店舗側にとって安定した収益が見込める点が、サブスクリプション型のビジネスモデルの魅力です。会員データを分析すれば、顧客の好みや来店パターンを把握でき、売上の向上にも役立ちます。
サブスクリプション型のビジネスモデルを導入すれば、来店客数の予測も可能です。食材の仕入れ量を最適化できるサブスクリプションによっては、フードロスも削減できます。顧客には、優先予約や特別メニューの提供を受けられるメリットがあります。システム構築などの初期コストが必要な点には注意が必要です。
外国人観光客の回復によるインバウンド需要

現在、訪日外国人観光客の96%が日本滞在中に飲食店を利用しており「食」はインバウンド消費の中でも大部分を占めています。外国人観光客の受け入れ体制の整備は、現代の飲食店にとって売上の安定化や新規顧客の獲得につながります。外国人観光客の集客に効果的な対応は、以下のとおりです。
- 多言語メニューの導入
- キャッシュレス決済への対応
- 宗教的・文化的な配慮
- 予約プラットフォームとの連携
観光客の国籍によって好みや食習慣が異なるため、来店が多い国の観光客に合わせたメニュー開発も効果的です。辛さの調整や食材の選定など、来店の多い外国人のニーズに応じた工夫が求められます。
地方や郊外での新たなビジネス
地方や郊外における飲食ビジネスでは、地域コミュニティとの関係構築と地元の特色を生かした店舗運営が成功の鍵です。地方や郊外での新たなビジネスには、以下のモデルが挙げられます。
- 地域のイベントと連動したポップアップ店舗
- ワーケーション需要を見込んだ滞在型カフェ
- 地元の生産者と連携した産直レストラン
- 空き家を活用した古民家カフェ
地元住民と観光客の両方をターゲットにした運営を行えば、安定した集客とリピーターの確保が期待できます。
» 自分に合った仕事の見つけ方を解説
今後の飲食業界のトレンド

今後の飲食業界では、ライフスタイルの多様化や価値観の変化に伴い、消費者のニーズに応える新たなトレンドが注目されています。重要とされている動きは、以下のとおりです。
- 健康志向と代替食品
- 体験型飲食店の可能性
- SNSを活用したマーケティング戦略
健康志向と代替食品
健康への関心が高まる中、20〜30代の若年層を中心に体に良い食材や食習慣を意識する傾向が強まっています。飲食業界でも、健康志向を反映したメニューの導入が求められています。飲食業界で注目されている健康食品は、以下のとおりです。
- オーガニック食品
- 大豆ミートなどの代替肉
- アーモンドミルクなどの代替乳製品
- 低糖質・低カロリー食品
健康とおいしさを両立させる工夫が、今後の集客やブランド価値の向上につながります。
体験型飲食店の可能性

体験型飲食店は従来の飲食店と比べて、顧客が能動的に参加しながら楽しめる新しい飲食スタイルとして注目されています。飲食業界で注目される体験は、食材収穫体験やVRを活用した没入型ダイニング、五感を刺激する演出などです。
顧客の思い出作りや特別な日の演出を重視したサービスの提供は、飲食店にとって他店との差別化を図るうえで武器になります。
SNSを活用したマーケティング戦略
若年層を中心に、情報収集や店舗選びにSNSを活用する傾向が強まっています。今後の飲食業界にもSNSを活用した戦略的な発信が求められます。効果的なSNSマーケティングを行うためのポイントは、以下のとおりです。
- ターゲット層に合わせたプラットフォームの選定
- 短尺動画コンテンツの定期的な発信
- 季節やトレンドに合わせた投稿
- インフルエンサーとのコラボレーション
- ハッシュタグキャンペーン
ユーザー生成コンテンツ(UGC)を活用し、来店客が自ら店舗や料理の写真を投稿したくなる仕掛けを作る必要があります。店内の「インスタ映えスポット」の設置や、写真を投稿した顧客への特典提供などが効果的です。
まとめ
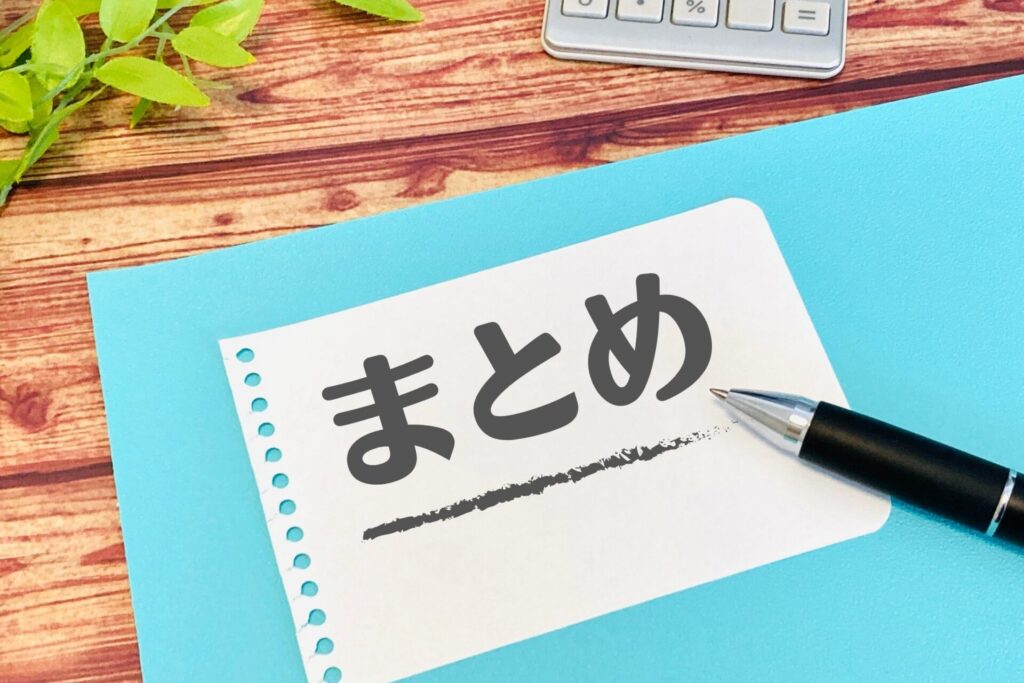
今後の飲食業界で生き残るためには、デジタル化やDX推進による顧客体験の向上が重要です。サブスクリプションモデルの導入やインバウンド需要の取り込みは、飲食業界での新たな収益源となる可能性があります。
健康志向やサステナビリティへの対応も、飲食業界における競争力を左右する要素です。転職を検討する際は、飲食業界の動向を踏まえたうえで、自身のスキルや経験をどう生かせるかを考えてみましょう。








